300mLって、どれくらいなのかな。
コップ一杯と言われても、器の大きさで迷いますよね。
このページは、身近なものだけで300mLをパッとイメージできるようにまとめました。
ペットボトルや缶、IKEAの30cLマグ、カップ麺のお湯などで置き換えて説明します。
日本と海外のカップ基準やスプーン換算もやさしく整理しました。
さらに、蛇口の秒数で量を合わせるコツや、マグに目印を作る小ワザも紹介します。
飲み物一杯、スープ一人分、調味の配分まで、今日から迷わず使えます。
一文ごと短く読み進められるので、必要なところだけ拾っても大丈夫です。
まずは、300mLの基本から見ていきましょう。
300mlってどれくらい?数字だけではわかりづらい容量を解説

300mlは何リットル?ccやカップとの換算も紹介
300mLは0.3リットルです。
300ccとも表現できます。
1mLは1cm³なので300mLは300cm³です。
1リットルは1000mLなので、300mLは全体の3割にあたります。
デシリットルでは3dL、センチリットルでは30cLと書けます。
商品ラベルで0.3Lや30cLの表記を見かけたら、どちらも300mLのイメージで大丈夫です。
日本の料理用カップは1カップ=200mLです。
300mLは1.5カップになります。
200mL+100mLという足し算に置き換えると、計量の段取りが楽になります。
200mLのラインまで注いで、そこから半カップ分を足す流れで整えます。
海外レシピでは1カップの定義が変わることがあります。
米国の一般的なカップは約240mL。
メートル法のカップは250mLです。
300mLはそれぞれ約1.25カップ、1.2カップの目安になります。
米国の液量オンスでは10fl ozが約296mLなので、300mLにとても近い量です。
換算で迷ったら、手元のメモに「日本200/米国240/メートル法250」と並べておくと、
次からすぐに照らし合わせられます。
大さじ・小さじ・米カップで300mlを量るには
日本の大さじは15mLです。
小さじは5mLです。
300mLは大さじ20杯または小さじ60杯です。
大さじと小さじを組み合わせるなら、大さじ19杯(285mL)+小さじ3杯(15mL)=ちょうど300mLという作り方もあります。
スプーンしかない日でも、落ち着いて数えれば合わせられます。
炊飯用の米カップは1合=180mLです。
1合に大さじ8杯(120mL)を足すと約300mLになります。
別解として、1合に大さじ6杯(90mL)+小さじ6杯(30mL)でも合計300mLになります。
手元の道具に合わせて、やりやすい手順をひとつ決めておくと迷いにくくなります。
計量は水平な台に置きます。
目線はメモリと同じ高さで読みます。
カップの内側の曲面は底のラインを見ると安定します。
最後は小さじで数mLずつ微調整すると、仕上がりがそろいやすくなります。
明るい場所で読み取ると、数字の確認がスムーズです。
料理用1カップ=200mL、米カップ1合=180mL。
手元の換算メモに並べておくと行き来しやすくなります。
gとmlは同じ?水とその他の液体との違いを知ろう
mLは体積の単位です。
gは重さの単位です。
同じ数値でも中身によって重さは変わります。
水はおおよそ1mL=1gとして扱えます。
300mLの水は約300gです。
牛乳は水よりわずかに重め、油は軽め、しょうゆやシロップは重めという傾向があります。
同じ300mLでも、素材ごとに重さが少しずつずれます。
料理でg表記をmLに変えるときは、まず水で基準を作り、
よく使う調味の目安をノートに残しておくと次回がスムーズです。
レシピの分量を写すときは、体積と重さが混ざらないように単位も一緒に書き写します。
身近なもので視覚化!300mlのイメージが湧く例

ペットボトルや缶飲料で例える300ml
500mLのペットボトルなら約6割が300mLの目安です。
350mL缶ならおよそ8割強です。
200mLパック飲料なら1本と半分で300mLのイメージです。
外出時に300mLボトルの飲料も見かけます。
そのままの容量を体で覚えやすいので目安になります。
550mLのペットボトルが並ぶ売り場では、およそ半分強が300mLです。
330mL缶は近いサイズなので、満杯で少し多めという感覚で覚えると扱いやすいです。
内容量185g(約185mL相当)の缶なら約1.6本で300mL相当です。
ラベルの容量表示を見て、手持ちのマグの満水ラインと照らし合わせるとイメージが定着します。
氷を入れる日は、氷の分だけ少し低めで仕上げるとちょうどよく感じられます。
二人で分けたい日は、150mLずつに分けると量の見通しが立てやすくなります。
IKEAマグや紙コップ10ozなど家庭にあるもので再現
30clと表示されたマグは300mLの目安です。
満水でだいたい300mLと覚えておくと便利です。
内側の形によって水位の見え方が変わるので、
最初に水300gで印を作っておくと合わせやすくなります。
30cLのほかに3dLや0.3Lの表記を見ることもあります。
どれも300mLとして扱えるので、手元のメモに並べて書いておくと迷いにくくなります。
10ozの紙コップは約295〜300mLとして流通しています。
満水なら“ほぼ300mL”の目安として扱えます。
商品によっては飲みやすい推奨ラインが別に描かれていることがあります。
満水と推奨ラインを見分けて、必要に応じてどちらを使うかを決めます。
マグや紙コップにマスキングテープで小さな印を付けると再現しやすくなります。
150mLの中間ラインも付けておくと、半量で作りたいときに便利です。
透明のカップなら外側に印、色付きのカップなら内側の目立たない位置に印を付けると見やすくなります。
カップヌードルのお湯の量=300mlという事実
標準のカップヌードルは300mLが多く、種類によっては320mLの例もあります。
内側のラインまで注ぐとおよそ指定量です。
商品ごとの差はパッケージ記載で確認します。
例:「カップヌードル」は300mL、「シーフード」は320mL、「あっさりシーフード」は310mL、「レッドシーフード」は300mLの目安です。
カップは机に置いて、目線をラインと水平に合わせると注ぎやすくなります。
500mLペットボトルの六割を目安にしても、近い量に合わせやすくなります。
10ozの紙コップを満水にすると、約295〜300mLで“ほぼ300mL”のイメージに近づきます。
マグの外側に小さな印を付けておくと、お湯を注ぐときのゴールが見やすくなります。
やかんや電気ケトルを使うときは先に300mLを量って入れると迷いません。
計量カップで300mLを作ってからケトルに移すと、注ぐ量をそろえやすくなります。
二杯分なら600mLを先に作っておくと、配分がスムーズになります。
普段使いのカップで印を作っておくと、繰り返すほど手の感覚でもつかみやすくなります。
詰め替え製品やスープジャーで見かける300ml
シャンプーやハンドソープでは300mLのボトルが多く見られます。
ボトル1本分がそのまま300mLの目安になります。
ラベルの内容量を見比べて、自分の使い切りのペースに合うサイズを選びます。
透明ボトルは残量が見えやすく、次の補充のタイミングをつかみやすいです。
ポンプ式は1回の目安量が記載されることがあり、回数でざっくり把握できます。
スープジャーには0.3Lのモデルがあります。
1食分のスープを入れるときにイメージがつきやすい容量です。
使う前にお湯で容器を温めておくと、注いだときの温度の落ち方がゆるやかになります。
具材は口径に合わせて小さめに切ると、スプーンですくいやすくなります。
満たす位置をあらかじめ決めて、線の少し下で仕上げると持ち運びのときに落ち着きます。
実生活で300mlを使う場面と応用例

飲み物としてのちょうどいいサイズ
お茶や水をコップ1杯飲みたいときに300mLはわかりやすい基準です。
作業中の小休憩にも多すぎず少なすぎない量です。
朝の白湯や食事前の一杯にも取り入れやすいボリュームです。
500mLボトルならおよそ六割が300mLの目安です。
350mLマグなら八分目くらいで近い量になります。
氷を入れる日は、印より少し下で仕上げるとちょうどよく感じられます。
温かい飲み物は、少しずつ注いで印まで合わせると落ち着いて準備できます。
プロテインやスポーツドリンクを作るときも目安になります。
パッケージの表示量に合わせて300mLの水量で作ると、計算がそろいやすくなります。
最初は大さじや小さじで足し引きしながら、好みの濃さを見つけます。
マグやシェイカーに300mLラインを付けておくと、外でも同じ仕上がりに近づけます。
二回に分けて飲みたい日は、150mLずつに分けると扱いやすくなります。
料理で使う水・出汁・調味料の目安量
だしやスープを作るときに300mLを基準にすると味の調整が楽になります。
計量カップとスプーンの組み合わせで手早く量れます。
レシピが600mLと書かれている場合は半量で300mLになります。
2人分→1人分に切り替えるときの換算にも使えます。
薄め液やタレを作るときも合計を300mLにすると配分を考えやすくなります。
三倍濃縮を300mLで作るなら、濃縮100mLと水200mLで合計300mLです。
四倍濃縮なら、濃縮75mLと水225mLで合計300mLです。
しょうゆベースの合わせ調味には、ベースを200mLにして、
みりんや砂糖を足して300mLに仕上げる方法もあります。
最後は小さじで味見しながら数mLずつ調整します。
次回の再現にもつながります。
炊飯やスープづくりでの300mlの使い方
米カップ1合の水は180mLです。
炊飯では好みで微調整しますが基準として覚えておくと便利です。
2合なら目安は360mL、3合なら540mLと、合数に合わせて足していくと考えやすくなります。
無洗米や玄米など種類によって加える量が変わることがあるので、
最初は少なめから試してノートに残します。
浸水の時間を一定にすると、出来あがりのイメージがそろいやすくなります。
スープは1人分で300mL前後にすると器に収まりやすくなります。
具だくさんにする日は250mLのだしに具を多め、
さらっと飲みたい日は300mLのだしに具を少なめなど、バランスを決めておくと整います。
器の直径と深さをメモして、どのくらい注ぐときれいに見えるかを一度確認しておくと安心です。
スープジャーを使う場合は満たすラインを決めておくと分かりやすいです。
最初にお湯で容器を温めてから、300mLのスープを注ぐ流れにすると落ち着いて準備できます。
朝の用意がスムーズになります。
前夜のうちに具材だけ入れておき、朝にだしを注ぐ方法も手際よく感じられます。
移動中に揺れてもこぼれにくいように、フタの閉まり具合を最後にもう一度だけ確かめます。
コーヒー抽出での300mlの活用と比率の目安
コーヒーはお湯の量と粉の量の比率が味わいに関わります。
300mLなら粉を15〜18gあたりから試す方法があります。
1:16〜1:18の比率を目安にして、少しずつ好みに合わせて動かします。
この比率はSCAの基準55g/L(±10%)に沿った目安です。
はじめに少量のお湯で20〜30秒ほど蒸らします。
その後は数回に分けて静かに注ぎます。
フィルターの紙の縁に直接かけず、中心からゆっくり円を描くと落ち着いた流れになります。
抽出はおよそ2分半〜3分前後を目安にします。
時間が長いと濃くなりやすく、短いと軽く仕上がりやすいので、記録しながら整えます。
挽き目は中細挽きから始めます。
時間が長いと感じたら少し粗く、短いと感じたら少し細かくします。
氷を入れたグラスに直接落とせば、出来あがりはひんやりとした一杯になります。
マグの満水量を把握しておくと仕上がりをイメージしやすくなります。
抽出後はマグの外側に付けた小さな印まで注ぐと、毎回の量がそろいます。
お気に入りの1杯を繰り返し作りながら、少しずつ自分の基準を育てていきましょう。
他の容量と比較してみよう!300mlの立ち位置

100ml/200ml/500mlとの比較図
100mLは大さじ約6杯と小さじ約2杯です。
小さじだけで量るなら約20杯です。
100mLは少量のソースづくりや試作に向くサイズです。
200mLは日本の1カップです。
計量カップの基準になっているので、レシピの把握がしやすい量です。
スープやだしの下ごしらえにも使いやすい容量です。
500mLは一般的なペットボトル1本です。
日本の1カップ換算だと2.5カップに当たります。
持ち歩きの飲み物や二人分の調理にちょうどよいことが多い量です。
300mLはこれらの中間に位置します。
100mLを三つ合わせた量、150mLを二つ合わせた量と覚えるとイメージしやすいです。
飲み物1杯、スープ1人分、ちょい足しのだしなど、日常で使う場面が多いサイズです。
器に注いだときの見た目もすっきりまとまりやすく、扱いやすい印象になります。
300mlと海外のカップ基準(US/UK/メートル法)
米国の一般的なカップは約240mLです。
300mLは約1.25カップです。
メーカーの表記では236〜240mLの幅で案内されることもあります。
丸め方によって小さな差が出るので、家では240mLとしてそろえておくと計算が楽になります。
メートル法のカップは250mLです。
300mLは1.2カップです。
豪州や欧州のレシピでは250mL基準がよく使われます。
ページ下部や材料欄に定義が載ることがあるので、
一度確認してから換算すると落ち着いて進められます。
英国ではmL表記が主流です。
fluid ounceの換算は米国と数値が異なるため、oz表記を見たときは単位の種類もチェックします。
自分用の換算メモを作って、よく使う数値だけを手元に置いておくと迷いにくくなります。
表記が異なると迷いやすいのでレシピやパッケージの前提を確認します。
一度表を作って手元に置いておくと便利です。
日本200mL、米国240mL、メートル法250mLという三本柱を書き分けておくと、
どのレシピにも合わせやすくなります。
容量の違いが買い物や収納の選び方に関わる理由
同じ商品でも内容量が異なる場合があります。
自分の使い切りペースに合う容量を選ぶとムダが抑えやすくなります。
一人分なら300mL前後、家族でシェアするなら500mL以上など、
暮らし方に合わせて目安を決めます。
週ごとの使用量を書き出して、棚に並べる本数を逆算すると選びやすくなります。
収納ではボトルの高さや直径も関わります。
300mLクラスのボトルはキッチンや洗面の棚に並べやすいことが多いです。
丸型は取り出しやすく、角型は並べるときに収まりがよい特徴があります。
トレーの幅や冷蔵庫の段の高さも合わせて測っておくと、入れ替えがスムーズになります。
ラベル面を手前に向けると、残量や種類をすぐに見分けられます。
300mlの理解がなぜ重要?知って得する生活の知恵

サイズ感をつかんでムダを減らすコツ
普段よく使う容器に目印を付けます。
300mLラインを一度作っておくと毎日の家事がスムーズになります。
キッチンスケールで水300gを注いで、目印の位置を決めます。
テープは細く切ると目立ちにくく、洗うときも扱いやすいです。
同じ容器をいくつか並べて、同じ高さに印をそろえると共有しやすくなります。
朝の支度で同じ順番で量る習慣にすると、手順が自然にまとまります。
マグ、スープジャー、水筒の三つを同じ基準にしておくと、外でも迷いにくくなります。
買い物メモに「300mL×何回」と書いて、在庫と合わせておくと選びやすくなります。
買い物の前に必要量をイメージします。
足りないときだけ追加する考え方にすると過不足が少なくなります。
一日や一週間で使う量をざっくり見積もります。
余りそうなら次回に回す、減りが早いなら小さいサイズを足すなど、柔軟に調整します。
定番アイテムは写真に撮って、容量表示をメモしておくと次も迷いにくくなります。
パッケージ選びや保存容器選びに役立つ
家族の人数や飲む回数に合わせて容量を選ぶと管理しやすくなります。
冷蔵庫の棚に合うボトル径や高さも合わせて確認します。
注ぎ口の形や開け閉めのしやすさも比べます。
丸型は洗いやすく、角型は並べやすい特徴があります。
棚の高さに合わせて、縦に長いボトルと短めボトルを使い分けます。
透け感のある容器は残量が見やすく、補充のタイミングをつかみやすいです。
ラベルに「300mLライン」と書いておくと、家族も同じ目安で使えます。
開封した日は小さなシールで控えておくと、使う順番を決めやすくなります。
保存容器は300mL基準と500mL基準をセットで持つと使い分けがしやすくなります。
中身の見える容器だと残量も把握しやすくなります。
300mLは一人分の副菜やスープの小分けに向きます。
500mLは二人分や翌日の取り分に向きます。
同じシリーズでそろえるとフタの互換性があり、片づけがまとまりやすくなります。
サイズが分かるように底面に小さく数字を書いておくと、取り出すときに迷いにくくなります。
水道の流量から300mlを時間で測るワザ
家庭の水栓は条件で約6〜20L/分(=100〜333mL/秒)と幅があります。
(東京都水道局の標準12L/分相当の数値も広く引用)
まず500mLの空ボトルを満たす時間を測り、自宅の“基準秒数”をメモします。
その秒数の六割が300mLの目安になります。
キッチンタイマーやスマホのストップウォッチを使うと合わせやすいです。
温水と冷水で流量が変わることがあるので、同じ条件で練習します。
正確に量りたいときは計量カップやキッチンスケールを使います。
慣れるまでは印を付けた容器で再確認すると安定します。
仕上げに小さじで微調整すると、狙いの位置に寄せやすくなります。
300mlに関するよくある質問(Q&A形式)
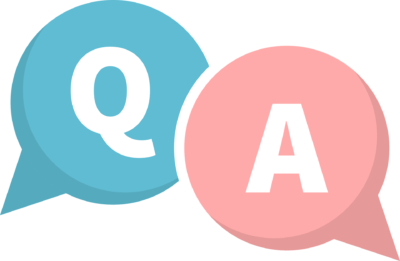
300mlの飲料は何本分?どんな製品がある?
350mL缶なら約8割強です。
500mLペットなら約6割です。
小型の300mLボトル飲料も売られています。
280mLや330mLのボトルや缶も見かけます。
250mL缶なら約1.2本で300mLの目安になります。
185mL缶コーヒーなら約1.6本分のイメージです。
ラベルの容量を見比べて、手持ちのマグの満水量と合わせると覚えやすくなります。
自販機やコンビニでよく見るサイズをメモしておくと、外出先でも見当をつけやすくなります。
紙パックは200mLが多いので1.5本でおよそ300mLです。
売り場の表示を見ながら選ぶと容量感がつかめます。
同じ棚に250mLや350mLの製品が並ぶこともあります。
迷ったときは、飲み切る量を思い浮かべて選ぶと気持ちよく使い切れます。
300mlの容器は機内に持ち込める?
機内持ち込みでは1容器100mL以下の規定が一般的です。
そのため300mLボトルは対象外になる場合があります。
詳しくは利用する空港や航空会社の案内で確認します。
液体物は透明の袋にまとめる決まりが示されることがあります。
袋の大きさや口の閉じ方に指定がある場合もあります。
経由地で基準が異なることがあるので、
出発前に最新の案内を見ておくと落ち着いて準備できます。
300ml入りの調味料や化粧品ってどんなもの?
しょうゆやソースの一部に300mLクラスのボトルがあります。
化粧水やハンドソープのボトルにも300mL前後のものがあります。
使う頻度に合わせて選ぶと管理がしやすくなります。
ドレッシングやめんつゆは250〜300mL帯の製品が並ぶことがあります。
台所用の洗剤やヘアケアの詰め替えにも、300mLクラスが用意されていることがあります。
棚の高さやトレーの幅と合わせて選ぶと、並べたときに収まりがよく見えます。
旅行用は50〜100mLが中心なので、詰め替えるときは容器の容量表示を見て合わせます。
300mlを体感する!自分で測ってみよう

自宅にあるもので300mlを正確に量る方法
200mLラインまで注いでから大さじ6杯と小さじ2杯を足します。
計量スプーンしかない場合は大さじ20杯で300mLです。
ゆっくり数えながら入れると、こぼれにくく落ち着いて作業できます。
スプーンはすり切りにしてから入れると、量がそろいやすくなります。
同じスプーンを使い続けると、手の感覚も整ってきます。
キッチンスケールで水300gを量り容器に移す方法も簡単です。
容器をゼロリセットしてから水を入れると、数字を見ながら合わせられます。
移し替えた位置に小さなテープで印を付けると、次からは見るだけで合わせられます。
口が広い容器を使うと注ぎやすく、こぼれにくくなります。
明るい場所で目盛りを読むと、読み違いを避けやすくなります。
よくあるつまずきは、カップを斜めに持ったまま読むことです。
台の上に置いて、目線をメモリと水平に合わせます。
水面のカーブは一番低い位置を目安にすると、数字が安定します。
最後は小さじで微調整すると、気持ちよくぴったりに近づきます。
おすすめの300ml計量グッズと活用法
200mLと100mLの目盛が見やすい計量カップは重宝します。
持ち手がついたものだと注ぎやすくなります。
透明なタイプは水位が見やすく、濃い色の液体でも読み取りやすいです。
外側と内側の両方にメモリがあるものは、持ち替えなくても確認できます。
注ぎ口が細いカップは、ボトルや水筒にも入れやすく感じられます。
大さじと小さじのセットは日常のほとんどの計量に対応します。
平らなカードの縁ですり切ると、量がそろいやすくなります。
保管はリングでまとめておくと、必要なサイズだけすぐに取り出せます。
スープジャー0.3Lは持ち歩きの基準づくりに役立ちます。
朝に満たした位置を覚えておくと、家でも外でも同じ量を再現しやすくなります。
折りたたみのじょうごがあると、こぼさずに移し替えやすくなります。
あなたのマグや水筒に300mlラインを作ろう
普段使いのマグに水を300g入れて高さを確認します。
その位置に小さな印を付けます。
これでマグが簡易の計量器になります。
印は目立ちすぎない色にすると、普段使いでも気になりにくくなります。
テープは細く切って、段差ができないように軽く押さえます。
写真に撮っておくと、別の容器で同じ高さを作るときの参考になります。
水筒も同じ方法で目安ラインを作れます。
外出時でも迷いにくくなります。
家ではメモリ付きのカップで作り、外では印を目安に仕上げる流れにするとスムーズです。
ボトルを洗ったあとに印が薄くなったら、同じ位置に貼り替えて更新します。
季節や気分に合わせてラインの色を変えると、気持ちも切り替えやすくなります。
知って楽しい!300mlに関する豆知識

なぜ日本のカップは200ml?意外な背景
日本の家庭料理で使いやすい基準として広まりました。
家庭の器やレシピで扱いやすい区切りです。
家電の取扱説明書や家庭科の教材でも同じ前提がよく使われます。
市販の計量カップと大さじ小さじの組み合わせがそろっていて換算しやすいです。
大さじ15mL×10杯で150mL。
さらに大さじ3杯で45mL。
小さじ1杯を5mLとして足し引きすると合計をぴったりにできます。
米カップの180mLとも行き来しやすいので、台所で迷いにくくなります。
混同を避けたいときは、ノートに「料理用200mL/米用180mL」と書き分けておきます。
よく使うカップやマグに薄い目印を付けて、自分の基準をそろえておくと手早く進みます。
海外では別の基準もあります。
レシピの前提を確認してから換算すると混乱が少なくなります。
米国は約240mLのカップ。
メートル法の国は250mLのカップ。
ページの脚注や材料表に定義が載っていることがあります。
見つからない場合は、まず240mLか250mLかを確かめてから手元の表に残しておくと、
次回もスムーズです。
10オンスは300mlじゃない!?単位の落とし穴
10fl ozは約296mLです。
ほぼ300mLですが完全に同じではありません。
紙コップやマグの表記を見るときは近い値として捉えると扱いやすいです。
製品によっては満水量と推奨の注ぎ量が別々に書かれていることがあります。
その場合は、どちらの値を基準にするかを最初に決めます。
あと少し足りないときは、小さじ1杯=約5mLを目安に調整します。
海外のマグに10ozと刻印されている場合は約296mLのイメージで扱います。
英国式のfl ozは換算が異なり、10fl ozで約284mLになります。
表記の種類を見分けてから作業すると、計算が落ち着きます。
数mLの差は家庭料理では大きくずれにくい範囲です。
気になる場合は計量スプーンで微調整します。
お店では9oz、12oz、16ozなどのサイズも並びます。
見かけた容量をメモしておくと、次に選ぶときの目安になります。
世界のカップ事情と300mlの立ち位置
米国は約240mLのカップが広く使われます。
オーストラリアなどでは250mLのカップが一般的です。
日本の家庭料理では200mL、炊飯では180mLの米カップという前提がよく登場します。
北欧や欧州ではmLやcL、dLの表記も多く、30cLや3dLは300mLを意味します。
この違いを知っておくと、海外のレシピやパッケージも読みやすくなります。
300mLはその中間にある扱いやすいサイズです。
レシピや容器の基準を意識して選ぶとスムーズです。
飲み物1杯やスープ1人分に使いやすく、保存容器の小分けにも向きます。
500mLと並べて常備すると、作る量やしまう量の調整がしやすくなります。
自分のキッチンでよく使うサイズを決めておくと、準備が整い、片づけも短時間でまとまります。
まとめ:300mlを理解すれば暮らしが変わる

飲み物や料理で役立つ“容量の目安”
300mLは飲み物1杯やスープ1人分の基準になります。
計量の手順を一度覚えると毎日の準備が整えやすくなります。
朝の白湯やお茶にも使いやすい量です。
作業の合間にひと息つきたいときも、ちょうど落ち着くボリュームです。
マグの満水量と合わせておくと、注ぐときに迷いにくくなります。
同じ器を使い続けると、手元の感覚がそろっていきます。
よく使うカップやマグにラインを付けておきます。
家でも外でも同じ基準で量れます。
マスキングテープを細く切って外側に小さく貼ると見やすいです。
消えにくいペンで目印を書いても扱いやすいです。
印は少し低めに付けて、注いでから微調整すると仕上がりがそろいます。
水筒やスープジャーにも同じ印をつけると、持ち歩くときも迷いません。
スマホで印の位置を撮影しておくと、別の容器で合わせるときの目安になります。
これからは「見ただけで300ml」がわかる!
身近なボトルやカップでイメージを積み重ねます。
今日から少しずつ容量感を育てていきましょう。
冷蔵庫のボトルを見たときに、あと何杯ぶんかを想像できます。
買い物のときも、どのサイズがちょうどよいかを見通しやすくなります。
同じ目安を家族や同僚と共有すると、準備や配分が整えやすくなります。
小さな習慣を積み重ねて、暮らしのリズムに合わせていきましょう。


