メジャーや商品ページで「1/2」と見かけて戸惑ったことはありませんか。
すぐに知りたい答えは12.7mm、つまり1.27cmです。
ただ、配管やねじでは同じ「1/2」でも実寸が違う場面があります。
このページはその違いをやさしく整理し、迷いを減らすための道しるべになります。
まずは換算の基本と覚え方を丁寧に確認します。
次に13mmとの違いを比べ、近いサイズをどう選ぶかを具体的に見ていきます。
ドリルやレンチの選び方、差込角の見方も一緒にチェックします。
配管の呼び径や規格の読み方も、例と短いメモで直感的に理解できます。
クレジットカードの幅を使って12.7mmをイメージする小ワザも紹介します。
買い物や作業の前にここだけ見返せば手順がすっと整います。
初めての方でも読みやすい順番で、必要なところからすぐに活用できます。
さっそく、あなたの場面にぴったりのサイズ選びを始めましょう。
この記事でわかること

1/2インチは何mm・何cmかの正確な換算
1/2インチは12.7mmで1.27cmです。
まずは答えを知ってから読み進めると全体像がつかみやすくなります。
覚え方は「1→25.4」「1/2→12.7」を小さなメモにして手元に置くことです。
買い物やDIYの前に一度だけ声に出して読み上げると、作業の流れが整います。
センチで考えたいときは1.27cmと覚えておくと選び替えが楽になります。
電卓では0.5×25.4と入力すれば同じ答えになります。
まずこの数字をしっかり押さえてから、呼び径や規格の章へ進むと理解がゆっくり深まります。
他の分数インチとmm換算の違い
1/4や3/8や5/8なども一緒に覚えると作業がスムーズになります。
よく使うサイズだけ先におさえるのがおすすめです。
たとえば1/4は6.35mm、3/8は9.525mm、5/8は15.875mm、3/4は19.05mmです。
よく登場する順に手帳やスマホに並べて書くと、すぐ取り出せます。
迷ったときは25.4の倍数で考えると計算が落ち着きます。
売り場では分数表記とミリ表記が並ぶことがあるので、最初に単位を確かめます。
使う場面を思い浮かべながら、必要な行だけを先に覚える方法もやりやすいです。
呼び径と実寸のズレによる注意点
配管やチューブでは「1/2」という表記が実寸と一致しない場合があります。
現物や規格表で数値を確認してから選ぶと迷いにくいです。
売り場のラベルにはNPSやDNやCTSなどの略語が書かれていることがあります。
外径や内径や肉厚のどれを見たいのかを決めてから数字を確認します。
継手やバルブを使う予定があるときは相手側の表記も一緒に控えます。
ノギスや簡易スケールがあれば外径を軽く測ると選びやすくなります。
用途に合わせて通したい部品のサイズやゆとりの度合いを先に考えます。
銅管やPEXでは同じ1/2でも外径が約15.9mmになる規格がよくあります。
鋼管では外径が約21.3mmの規格があり呼び径と実寸が離れています。
迷ったときは品番で検索してメーカーの寸法表を確認します。
購入前に必要な寸法を小さなメモにまとめておくと選択がスムーズです。
工具・配管・材料の現場での使い分け
ネジやレンチやドリルなど、分野によって見方が違います。
この記事ではよくある場面をやさしく整理します。
ねじは軸の呼びで確認しレンチは二面幅で選びます。
ラチェットは差込角をそろえソケットは口径で合わせます。
ドリルは実際に開く穴径で選び素材に合う先端形状を選びます。
配管は呼び径と接続ねじの種類をそろえます。
合板は名目厚と実厚を見比べてカット幅を決めます。
仮組みで通りや収まりを確かめてから本番に進みます。
数値や品番はノートやスマホに記録すると次回の買い足しが楽になります。
1/2インチはmmで何センチ?すぐ知りたい人向けまとめ

1/2インチ=12.7mm=1.27cm(正確換算)
1インチは25.4mmです。
半分の1/2インチは12.7mmで、センチでは1.27cmになります。
最初に答えを確認してから読み進めると、全体のイメージがつかみやすくなります。
買い物やDIYで分数の表記を見かけたら、この数字を思い出してみてください。
メモに書いて手元に置いておくと、サイズ選びが落ち着いて進みます。
換算の計算式と覚え方
インチからmmは「インチ×25.4」で計算します。
インチからcmは「インチ×2.54」で計算します。
「25.4」と「2.54」をふせんにメモして手元に置くと便利です。
暗算では「×25」と「×0.4」に分けると考えやすくなります。
たとえば0.5×25.4は、0.5×25と0.5×0.4を足して12.7になります。
1/4は0.25なので、0.25×25.4は6.35になります。
cmで知りたいときは「×2.54」だけで済みます。
cmからmmに移すときは「×10」で小数点をひとつ動かします。
ふせんに
- 「1→25.4」
- 「1/2→12.7」
- 「1/4→6.35」
と並べておくと、売り場でもすぐ確認できます。
スマホのメモに小さな表を作っておくのもおすすめです。
作業の前に一度声に出して読んでおくと、手が動かしやすくなります。
インチとミリの換算をざっくりおさらい

1インチ=25.4mmの定義とは?
世界共通の基準として1インチは25.4mmと定められています。
これは国際合意の定義値です。
設計や表示でもこの値を使うのが基本です。
この数値は小数点以下まで固定の定義なので、掛け算でそのまま使えます。
インチをmmにしたいときは「×25.4」で計算します。
cmで知りたいときは「×2.54」で計算します。
メモに「1→25.4」「1/2→12.7」と書いて机やスマホに貼っておくとすぐ引けます。
分数が苦手でも大丈夫です。
1/8や1/16のように小さな単位は、倍にすると1/4や1/2に近づきます。
まずは1インチの基準を覚えて、そこから少しずつ広げていきましょう。
1/4、3/8、5/8など他のインチもチェック
1/4インチは6.35mmです。
3/8インチは9.525mmです。
5/8インチは15.875mmです。
3/4インチは19.05mmです。
少しずつ目を慣らしていきましょう。
覚え方のコツは「1/8=3.175mm」を基点に、2倍で1/4、3倍で3/8、5倍で5/8に進める方法です。
3/16は4.7625mmです。
5/16は7.9375mmです。
7/16は11.1125mmです。
9/16は14.2875mmです。
見かける頻度が高いサイズだけ先に押さえると混乱しにくくなります。
作業前にメモを手元に置くと迷いが減ります。
すぐ使える!インチとmmの換算表一覧
1/8インチは3.175mmです。
3/16インチは4.7625mmです。
1/4インチは6.35mmです。
5/16インチは7.9375mmです。
3/8インチは9.525mmです。
7/16インチは11.1125mmです。
1/2インチは12.7mmです。
9/16インチは14.2875mmです。
5/8インチは15.875mmです。
3/4インチは19.05mmです。
1インチは25.4mmです。
必要な行だけ印をつけておくと、その場で見返しやすくなります。
素材や場面に合わせて、よく使う列を自分用にまとめておくと便利です。
1/2インチの“落とし穴” 呼び径と実寸のズレに注意!
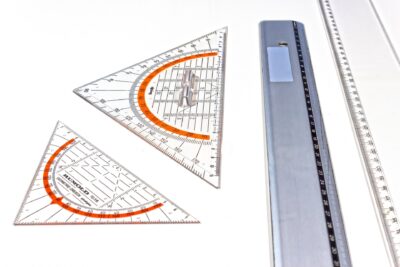
配管サイズの1/2インチは21.3mm!?
配管の「1/2」は呼び径という区分で、実際の外径は約21.3mmです。
「12.7mm」とは違うため、継手や部材を選ぶ前に数値を確認しましょう。
同じ1/2でも内径は肉厚で変わり、用途により流量のイメージも変わります。
表記ではNPS 1/2やDN15と書かれることがあり、読み方に慣れると売り場で迷いにくくなります。
NPS 1/2 は国際表記で DN15 に対応し、外径は 21.3mm(=0.840 in)で一定です。
継手は1/2-14 NPTなどの表記が入り、ねじの種類までそろえると組み合わせやすくなります。
外径を軽く測ってから選ぶと、近い品番の中から狙いを絞りやすくなります。
素材違いで外観が似ていても規格が異なることがあるので、ラベルの略号も一緒に見ます。
銅管やPEX管の1/2は実は15.9mm前後
給水用の銅管やPEX管では「1/2」の外径が約15.9mmの仕様が一般的です。
同じ「1/2」でも分野によって基準が異なる点を覚えておくと迷いません。
銅管はASTM B88の区分があり、PEXはCTSという系統で表記されることがあります。
これらの規格では1/2の実外径が0.625インチ(15.875mm)と定義されています。
継手は1/2 CUや1/2 PEXのように素材名が入ることがあり、組み合わせの目印になります。
圧着リングや差し込み式など、接続方式に合わせた部材選びが必要です。
器具側の呼びと配管側の呼びが違うときは、変換の継手を挟むとつながります。
店頭のサンプルで外径を当ててから買うと、戻りの手間を減らせます。
ボルトの1/2インチは工具サイズと違う
「1/2ボルト」は軸の呼び径が12.7mm相当という意味です。
六角頭を回すレンチは3/4インチや19mmを使う場面が多く、表記と工具が一致しないことがあります。
標準六角の1/2ボルトは二面幅3/4インチ(約19.05mm)が一般的で、重六角では7/8インチ(約22.2mm)となる場合があります。
ねじの規格には1/2-13や1/2-20などがあり、山の細かさが用途で変わります。
レンチの口は二面幅を基準に選び、刻印の数字を見てから合わせると手早く揃います。
口の合いがゆるいと角を傷めやすいので、ぴったりのサイズを選びます。
工具の差込角の1/2という表記は別の意味で、ソケットとの接続部の寸法です。
差込角と口径の数字を分けて考えると、組み合わせの迷いが減ります。
工具や穴あけ作業で“試してみる価値あり”なシーン

13mmで1/2インチは代用できる?
1/2インチの12.7mmに対して13mmは差が0.3mmあります。
木材などでゆとりがあっても、きっちり合わせたい場面では専用サイズを検討しましょう。
板材の通し穴なら誤差が小さくても通ることがあります。
金属の位置決めやはめ合いではわずかな差でも仕上がりに影響が出ます。
迷うときは端材で試し穴を作り、ボルトやパーツを通して感触を確かめます。
面取りを軽く入れると通しやすさが変わります。
座金を併用すると座面の擦れが落ち着きます。
固定後にガタつきがないか、指で軽く動かして確認します。
仕上がりを整えたい場合は12.7mm相当の工具を優先します。
作業のスピードを重視する場合は手持ちの13mmで仮合わせを行い、最終穴だけ専用で仕上げます。
1/2インチのドリルビットの選び方
英語表記のドリルセットなら「1/2」を選ぶと12.7mmで開けられます。
ミリ表記しかない場合は13mmになるため、仕上がりのゆるさを想定して選び方を考えます。
金工では小さめの下穴から段階的に広げると真円に近づきます。
木工ではスパイラルビットやフォスナービットなど、素材に合う先端形状を選びます。
板の裏側に当て木をするとバリが出にくくなります。
位置がずれやすいときはセンターポンチで軽く印を付けます。
深さを一定にしたいときはマスキングテープで目印を付けます。
口元は面取りビットで軽くさらうと仕上がりが整います。
穴径がシビアなときはステップドリルで微調整します。
ステンレスなど硬めの材は低速でゆっくり進めます。
潤滑を使う場合は少量でこまめに補います。
仕上がりの見た目を大切にしたいときは、最終工程だけ新品の刃を使います。
1/2インチボルトに合うレンチサイズとは
六角ボルトの頭には3/4インチのソケットがよく使われます。
メトリックでは19mmが近く、手持ちの工具と合わせて選べます。
六角の角が丸くなりにくいのは六角対辺にぴったり合う口です。
12ポイントよりも6ポイントのソケットは食いつきがやさしく感じられます。
狭い場所ではオフセットが小さいレンチが扱いやすいです。
動かしにくいときは延長バーで持ち手を長くすると回しやすくなります。
ボルトの規格は1/2-13や1/2-20などがあり、ねじ山は用途により異なります。
頭の二面幅は同じでも軸のねじは別なので、表記を見て部品をそろえます。
締め込みの最後は短いストロークでゆっくり整えます。
組み合わせ面に座金を入れると当たりが安定します。
作業後は工具を布でふいて収納すると次回の着脱がスムーズです。
間違いやすい表記・用語・規格を解説

呼び径と実寸を図で理解しよう
呼び径はグループ名のようなものです。
実寸の直径とは別物なので、表記だけで判断せず数値を確認します。
たとえば配管の1/2は外径が約21.3mmになる規格があり、12.7mmとは一致しません。
銅管やPEXでは外径が約15.9mmになる呼びがあり、分野ごとに前提が変わります。
ねじでは軸の呼びと六角頭の二面幅が異なるため、どの寸法を指しているかを意識します。
図では外径と内径を二重円で描き分けると違いがつかみやすくなります。
パッケージの表記は「NPS 1/2」や「DN15」や「CTS 1/2」などの略語が使われます。
見慣れない記号はメモに残し、次回の買い足しで迷わないようにしましょう。
NPTとBSPの「1/2」は互換性なし
NPTとBSPはねじの角度や密封の考え方が異なります。
同じ「1/2」でも組み合わせると合いにくいため、規格をそろえて選びます。
NPT は山角 60°、BSP は 55°で、BSP の平行ねじは「G」、テーパーは「R」で表記されます。
表記では「1/2-14 NPT」のように山数が入り、BSPは「G1/2」や「R1/2」と書かれることがあります。
この「14」は1インチ当たりの山数(TPI)を示します。
見分けに迷ったら現物の表記を探し、同じ規格の継手どうしで合わせます。
シールテープやシール剤を使う位置も規格で考え方が変わるため、説明書の指示に沿って準備します。
木材・合板の「1/2」は実厚と違うことも
合板では「1/2」と表示しつつ実厚が約11.9mmになることがあります。
カット寸法や溝幅は実測値に合わせると仕上がりがそろいます。
店頭では「1/2 nominal」と「15/32」などの表記が並ぶ場合があります。
北米ではPerformance Categoryとして「15/32」や「1/2」が並記され(PS 1 / APA)、
15/32は換算上約11.9mmで、表示厚さは0.451 in(約11.46mm)と記される例が一般的です。
厚みはロットや仕上げでわずかに差が出ることがあるため、定規やノギスで確認してから加工すると段取りがしやすいです。
スライドレールや金具の溝幅は実厚に合わせて調整すると収まりがよくなります。
棚板や箱物は、接合部のクリアランスを少しだけ見込んで設計すると組み立てやすくなります。
インチとミリの実用例・おもしろ豆知識

ラチェットレンチの「1/2」は差込角!
工具の「1/2」はソケットの差込角を示します。
口径とは別なので、ソケットのサイズと合わせて選びます。
差込角はハンドルとソケットをつなぐ四角い部分の一辺の長さです。
一般的には1/4、3/8、1/2の順で大きくなります。
1/2は中くらいから少し力のいる作業向けとして使いやすいサイズです。
ハンドルとソケットは同じ差込角で組み合わせます。
サイズが違うときはアダプターで合わせる方法もあります。
たとえば3/8のハンドルに1/2のソケットをつけたい場合は変換アダプターを使います。
ソケットの口径は回すボルトやナットの幅です。
差込角の数字と口径の数字は別の意味なので、両方を見て選ぶと迷いません。
保管するときは差込部を軽く拭いておくと着脱がスムーズです。
クレジットカードで12.7mmを感覚測定
カードの横幅は約85.6mmです。
1/2インチの12.7mmはおよそ幅の7分の1程度で、目安としてイメージしやすくなります。
カードは書類の上に置いて測ると扱いやすいです。
端から端までを定規で測り、七等分を目で追うと12.7mmの感覚がつかめます。
付箋やマスキングテープに12.7mmの印を付けておくと、現場でサッと比較できます。
スマホのメモに「1/2=12.7mm」と入れておくのも便利です。
きっちり測りたいときは定規やノギスを使い、ざっくり知りたいときはカードでイメージをつかむと使い分けできます。
ホームセンターの表記はどっちの単位?
売り場では同じ棚にインチとミリが並ぶことがあります。
パッケージの単位をよく見て、手持ちの工具や部材とそろえると迷いません。
インチは分数表記、ミリは小数表記が多いので、棚札の数字の並びで見分けられます。
ボルト売り場では「M12」などのミリ表記と、「1/2-13」などのインチ表記が別コーナーになっていることがあります。
ドリルビットはパッケージやシャンクの刻印に単位が書かれています。
同じ棚でもブランドによって表記が違うため、品番の数字だけで判断しないようにしましょう。
迷ったら手持ちの部材の表記をメモして持参すると、選び替えがスムーズです。
変換が必要なときは、25.4の早見メモを取り出して確認します。
まとめ:1/2インチ換算を正しく理解して使いこなそう

よくある勘違いの整理
「1/2=12.7mm」は長さ換算として正しいです。
ただし配管や銅管やPEXや合板などは名目表記で、実寸は別になる場合があります。
同じ数字でも分野ごとのルールが異なることを最初に意識しておくと迷いが減ります。
売り場のラベルだけで判断せず、外径や内径などの数値を確認すると目的に合いやすくなります。
ねじは軸の呼びと工具の口径が違うことがあり、表記と使う道具が一致しない場合があります。
作業前に単位と規格の表を見比べて、今回の用途に合う行をチェックしておくと進めやすいです。
換算表や図解でミスを防ぐ
よく使うサイズだけでも手元に表を置いておくと心強いです。
作業前にひと目で確認できる仕組みを用意すると迷いにくくなります。
定規の写真や図をノートに貼っておくと、数値のイメージがすぐつかめます。
1/2と13mmの差など、よく迷う組み合わせに印を付けると判断が速くなります。
スマホに換算メモを保存しておくと、売り場でも落ち着いて選べます。
定番の分数だけでも一覧化しておくと、家事やDIYのときに役立ちます。
1/2インチ関連サイズも覚えておくと便利
- 1/4は6.35mmです。
- 3/8は9.525mmです。
- 3/4は19.05mmです。
少しずつ覚えていけば十分です。
- 5/8は15.875mmです。
- 7/16は11.1125mmです。
- 5/16は7.9375mmです。
身近な作業でよく使う順番でメモすると、自然に覚えられます。


