雨の日や荷物が多い日、寝かしつけたまま移動したい時こそ、
ベビーカーを畳まずに乗れたら助かりますよね。
この記事は、タクシーでの“そのまま”利用をわかりやすく整理しました。
UDタクシーやJPN TAXIの呼び方、アプリの備考テンプレ、乗り降りの動線づくり、
サイズの目安までをコンパクトに確認できます。
状況に合わせた使い分けも紹介します。
今日の外出が少し軽くなるヒントをどうぞ。
初めての方でも準備リストで迷いません。
備考の書き方サンプル、合流しやすい場所の選び方、スロープ展開の段取りも具体的に。
東京・大阪・名古屋・福岡の手配先のヒントや、雨の日の工夫、忘れ物への連絡手順までカバー。
読後は自分のスタイルで呼び方を選べるように。
小さな移動も、遠出も、親子のペースで進めましょう。
必要なところだけ真似すれば十分です。
本稿は参考情報の共有であり、個別の判断や手配は読者の裁量でご確認ください。
- はじめに:タクシーでベビーカーはそのまま乗せられる?
- ベビーカーOKなタクシーが少ない理由とは?
- タクシーでベビーカーを“そのまま”乗せるには?
- そのまま乗せる vs 畳んで乗せる|どっちが正解?
- UDタクシー・JPN TAXI・子育てタクシーの違いとは?
- 配車アプリ別|“ベビーカーそのままOK”の呼び方
- そのまま乗るなら知っておくべき「ベビーカーのサイズと制限」
- ベビーカーとチャイルドシートは併用すべき?
- 乗車時の流れとスムーズに使うコツ
- 赤ちゃん連れのタクシー移動に役立つグッズ5選
- ベビーカーそのまま乗車が可能なエリアまとめ(主要都市)
- タクシー利用時によくある困りごとと対処のヒント
- おわりに:子どもとの移動をもっとラクにするために
はじめに:タクシーでベビーカーはそのまま乗せられる?

キーワード検索の背景:「そのまま乗せたい」親のニーズとは
ベビーカーを畳まずに移動したい時があります。
荷物が多い日や、寝ている子を起こしたくない場面です。
目的地までスムーズに進みたいという声も多いです。
この記事はその気持ちに寄り添って整理します。
結論:そのまま乗せられるタクシーは“限られる”が可能な方法はある
一般のセダン型は畳んで積む運用が中心です。
一方でUDタクシーなどの車両なら、そのままの運用に近い形が選べる場合があります。
配車アプリでの車種指定や乗降場所の工夫で実現しやすくなります。
この記事では使い分けと手順をわかりやすくまとめます。
本記事の対象読者とゴール
乳幼児と外出する保護者の方を想定しています。
初めて配車アプリを使う方も読み進めやすい構成です。
読了後に自分の状況で何を選べばよいかが整理できる状態を目指します。
本記事は一般的な情報の整理です。
実際の対応は地域のルールや事業者の運用、当日の状況により変わります。
最終的な判断はご自身でご確認ください。
ベビーカーOKなタクシーが少ない理由とは?

車いす用=ベビーカー用ではない?構造上の違い
UDタクシーは車いすでの乗降や固定を前提に設計されています。
固定具や寸法は車いす基準で決まっています。
ベビーカーは形状や重心が多様で想定が異なります。
この違いが運用差につながります。
床面のフラットさや固定金具の位置は、車いすのフレーム形状をもとに配置されています。
ベビーカーは折りたたみ機構やキャノピー、
荷物フックなどで重心が上下しやすい特徴があります。
三輪と四輪、単体用と双子用でも横幅と奥行きが大きく変わります。
ハンドルの角度やフットレストの高さで当たり方が変わるため、
向きや位置を試して収まりを探します。
ホイールのロックをかけ、小物は先にバッグへまとめるとその場の調整がしやすくなります。
事前に「横幅・奥行・高さ・畳み可否」をメモし、備考に一行で書くと伝達が端的になります。
運転手さんとは「入れる向き」「降ろす順番」を短い言葉で共有してから進めます。
事業者による対応差・台数制限の現実
UDタクシーの配備数は地域や会社で差があります。
時間帯や天候で手配しにくい場合もあります。
そのため事前の呼び方や備考の伝え方が結果を左右します。
中心部は台数が多めでも、通勤時や雨天は集中しやすい傾向があります。
郊外や深夜は配備が限られることがあり、早めの手配が役に立ちます。
アプリの「こだわり条件」と備考の併用で希望が伝わりやすくなります。
合流地点は屋根のある車寄せや広いロータリーを地図ピンで示します。
再配車が必要になった時のために、別アプリや別会社も候補に入れておきます。
当日の流れをメモに残し、次回の呼び方(車種・合流場所・備考文)を更新していくと準備が整えやすいです。
タクシーでベビーカーを“そのまま”乗せるには?
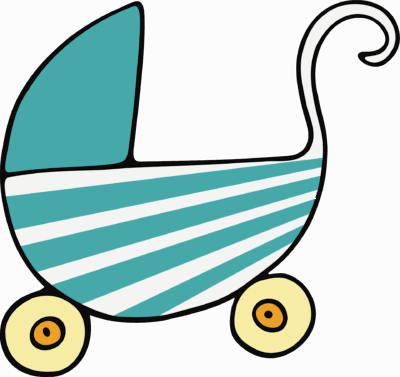
一般タクシーは「畳んでトランク」が基本
セダン型は荷室に畳んで積む流れが多いです。
乗車前に畳みやすい位置で準備すると進行が早くなります。
取り出しやすい順に荷物をまとめておくと降車がスムーズです。
ハンドルやフットレストなど出っ張りやすい部分は先に畳んで形を整えます。
小物トレーやカップホルダーは外してポーチに入れておきます。
ホイールの向きとロックをそろえると、トランクに入れやすくなります。
雨の日はベビーカーを袋で軽く覆い、布類は別袋に分けます。
先にスーツケースや食料品、次にベビーカーの順で載せると動線が短くなります。
到着の少し前になったら、再展開の準備を心づもりしておくと流れが整います。
UD(ユニバーサルデザイン)タクシーなら条件付きでOK
スライドドアと広い開口が特徴です。
平らで広めの場所なら乗り降りが行いやすいです。
車いす想定の寸法を参考に、ベビーカーのサイズも確認します。
スロープの角度や置き場所は運転手さんと一言で共有します。
前向きと後ろ向きで収まりが変わるため、その場で向きを試します。
車輪のロックをかけ、ハンドル高さを一段下げると扱いやすくなります。
荷物は先に車内へ移し、通り道を空けてから本体を入れます。
混雑時は一度畳んで乗り、到着地で広げ直す方法も選べます。
次回に備えてサイズと呼び方のメモを残しておくと手配がスムーズです。
UDタクシーでそのまま乗せる際の注意点と限界
スロープ展開にはスペースが必要です。
スロープは平坦で十分な幅のある場所だと準備が進めやすいと案内されています。
雨や傾斜が強い場所では作業が進みにくいことがあります。
固定は車いす前提のため、ベビーカーでは配慮が求められます。
運転手さんと手順を共有してから進めると落ち着いて対応できます。
地面の状態を軽く確認して、凸凹や水たまりを避けます。
人通りが多い時は一歩下がる位置を決めて順番に動きます。
スロープの角度は歩道との段差に合わせてゆっくり調整します。
周辺に荷物を置かず、通り道を空けておくと進行しやすいです。
レインカバーやタオルを先に取り出して、濡れやすい部分をカバーします。
風が強い日はハンドルを一段下げて持ちやすくします。
固定がむずかしい時は、折りたたんで積む方法に切り替えます。
出発前に降車時の流れも一言確認しておくと整いやすいです。
トヨタ公式サイトでは耐荷重200kg/300kgのスロープ仕様が公開されています。
重量の数値はトヨタ資料の記載に基づくもので、
GOヘルプには重量数値の明記は見当たりません。
子どもはベビーカーに乗せたままでOK?(利用時の配慮ポイント)
走行中は座席を使う方が動きが少なくて済む場合があります。
シートベルトの有無や座り方は車内の環境に合わせて判断します。
JAFの検証では、抱っこ状態は保持が続けにくい結果が紹介されています。
状況により判断は変わるため、当日の様子に合わせて検討します。
状況に合わせて無理のない方法を選びます。
事業者の案内では、車内ではいったん畳んで座席を使う運びを示す例が見られます。
“そのまま”は現場での収まりや運用により対応が分かれるため、
事前に伝え方を整えると選びやすくなります。
子どもが座れる場合は、座席で落ち着ける姿勢を探します。
眠っている時は、到着前にゆっくり体勢を整えます。
ベルトや肩紐がねじれていないかをさっと確認します。
日差しが強い時は、帽子やブランケットで光をやわらげます。
必要な物は手元に集めて、姿勢の変更回数を減らします。
乗り降りの直前に声かけをして、気持ちの準備を整えます。
到着地の環境に合わせて、ベビーカーへ戻すタイミングを選びます。
そのまま乗せる vs 畳んで乗せる|どっちが正解?

乗車時間・荷物・子どもの月齢別で使い分け
短距離なら畳まずに動線重視という選択があります。
長距離や荷物が多い日は畳んで座席確保が進めやすいです。
月齢やその日の機嫌によっても最適は変わります。
家族の体力や天候も考えて選びます。
徒歩移動が多い日はベビーカーを主役にして動線を短くします。
雨や日差しが強い日は屋根のある乗車位置を選ぶと準備が整います。
きょうだいがいる日は手をつなぐ役割や荷物担当を先に決めます。
乗り換えや寄り道が多い日は畳みやすさや取り出しやすさを重視します。
「畳んだ方がスムーズだった」ユーザーの声
目的地での準備時間が短くなるという声があります。
荷物が散らばりにくいという利点もあります。
一方で寝ている時はそのままが助かったという声もあります。
体験談を参考に当日の優先事項を決めます。
雨の合流口では畳んで乗った方が身支度が整えやすかったという声もあります。
駅の車寄せではそのまま乗れて合流が早かったという話もあります。
買い物帰りは座席を確保すると落ち着いて荷物の整理がしやすかったという感想もあります。
子の眠気やお腹の空き具合で選び方を変えると移動が穏やかだったという意見もあります。
UDタクシー・JPN TAXI・子育てタクシーの違いとは?

UDタクシー:国の基準を満たした車両(主にJPN TAXI)
国交省の標準仕様では、
乗降口の開口は幅800mm以上・高さ1300mm以上、
車いす固定スペースは長さ1300×幅750×高さ1350mm以上が示されています。
車いす固定のための装備が設定されています。
この仕様は車いす前提の基準で、ベビーカーの“そのまま固定”は制度上の想定外です。
床面が比較的フラットで、乗り降りの動線を取りやすいつくりです。
スロープは平らな地面だと扱いやすく、十分な横幅がある場所を選ぶと進めやすいです。
ベビーカーは前向きと後ろ向きで収まり方が変わるため、その場で向きを調整します。
ハンドルの角度を一段下げると当たりにくくなる場合があります。
備考欄に「ベビーカーあり」「合流場所は○○ロータリー」など具体的に書くと準備が整います。
JPN TAXIの実際の使い心地とベビーカー積載例
スライドドアで開口が広く、出し入れがしやすいです。
折りたたみベビーカーは荷室に収めやすい寸法感です。
二人乗りベビーカーはサイズ確認を先に行うと進行がなめらかになります。
室内にゆとりを感じられるつくりで、乗り込み時の姿勢を整えやすいです。
荷室では縦置きと横置きのどちらが収まるかを試し、ロックがかけやすい向きを選びます。
フレームとシートを軽く分けると、置き方に余裕が生まれることがあります。
荷物は先に車内へ入れて動線を空け、最後にベビーカーを調整します。
目的地付近では広い降車場所を選び、降ろす順番を簡単に共有します。
子育てタクシーの特徴(予約制・チャイルドシート対応)
子育て支援に配慮した研修を受けた乗務員が対応します。
予約制で荷物のサポートや寄り道の相談がしやすいです。
チャイルドシートの持ち込み前提か、事業者備え付けかを確認します。
予約はアプリや電話で受け付けており、連絡時に年齢や身長の目安を伝えます。
乗車時の手伝いが必要かどうかも一言添えます。
固定方式の希望(ISOFIXやベルト固定)や取り付け位置の希望も共有します。
支払い方法や領収書の有無を先に決めておくと精算が短時間で済みます。
復路の再予約が必要なら、到着前に相談しておくと当日の流れが整います。
配車アプリ別|“ベビーカーそのままOK”の呼び方

GOアプリでJPN TAXIを指定する方法
GOでは車いす対応車両は予約(AI予約)では選べません(『今すぐ呼ぶ』で指定できます)。
車両タイプの指定は『今すぐ呼ぶ』で[スライドドア車両/車いす対応車両]を選択可能で、
AI予約では車両タイプや会社の指定はできません。
備考にベビーカーありと記入して伝わりやすくします。
同乗できる人数や座席運用は車両や会社の取り扱いで異なります。
注文時にアプリの案内と会社の方針を確認してください。
地図ピンは停めやすい広めの場所を選びます。
混みやすい時間帯は早めに手配して待ち時間を短くします。
備考に「畳めます/畳めません」「横幅〇〇cm」と数字で書きます。
屋根のある乗車位置や車寄せの名称があれば一緒に書きます。
支払い方法と電子レシートの設定を先に済ませます。
到着直前に目印の看板や出口番号を短くメッセージします。
再配車の際は同じ備考文をそのまま再利用すると手早いです。
予約機能の種類によっては、車両タイプ指定の対象外となる場合があります(最新の仕様はGOアプリ内ヘルプでご確認ください)。
S.RIDEでスライドドア・車いす対応車両を呼ぶ方法
アプリ設定からスライドドア車の希望を入れます。
地域によっては事前確定運賃やネット決済が使えます。
履歴と電子レシートが後から確認できて便利です。
会社指定や車種優先の設定が使える地域もあります。
ルートメモに「屋根のある車寄せ希望」と一言添えます。
連絡はアプリ内通話やメッセージを使います。
迎車位置は建物名と入口名まで書くと合流しやすくなります。
クーポンやポイントの適用順は決済前に確認します。
到着時はトランクの開閉サポートをお願いする一言を添えます。
機能名は『車種指定』『事前確定運賃』『電子領収書発行』として案内されています。
事前確定運賃・手配料の注意点
出発前に概算が見えて予定が立てやすくなります。
乗車後に目的地やルートを変更した場合、
事前確定運賃は適用外となりメーター運賃に切り替わります。
有料道路料金は事前確定額に含まれず別立ての精算です。
S.RIDEでは到着後おおよそ5分で待機やキャンセルの扱いが生じる案内があり、乗車後にルートを変更すると事前確定からメーターへ切り替えとなる旨が示されています。
有料道路料金は別立てです。
手配料や時間帯加算の有無も合わせて確認します。
迎車の取り扱いや空港定額の対象エリアも見ておきます。
(上記に伴い)有料道路料金は別立てで精算される扱いがあります。
支払い方法も合わせて確認します。
キャンセル時刻の基準やキャンセル料の扱いもチェックします。
クーポンやポイントの適用順序は決済前に確認します。
領収書の宛名や用途が決まっている場合は先に設定します。
S.RIDE公式では、乗車後に目的地やルートを変更した場合は事前確定の適用外となりメーター運賃に切り替わり、有料道路料金は別建てでの取り扱いと案内されています。
呼びやすくするコツ(スムーズに合流するために)
停めやすい場所を指定して作業を簡潔にします。
合流の目印を短く伝えます。
ベビーカーの形状や畳む可否を先に伝えます。
サイズや重さの目安を数字で書くと伝わりやすいです。
事業者のルールに沿って協力的に進める姿勢が大切です。
必要なら「人手が必要です」と一言添えます。
停めにくい場所では数十メートル移動する提案をします。
再配車の際は車種希望と合流場所をより具体的に記します。
到着時刻の目安を共有し、メッセージ通知をオンにします。
短いお礼の言葉を添えるとコミュニケーションが穏やかになります。
そのまま乗るなら知っておくべき「ベビーカーのサイズと制限」

JPN TAXIの車いす乗車スペースの寸法
(事業者例の目安)標準的な車いすは長さ1200mm以内・幅700mm以内・高さ1300mm以内と案内されるケースがあります。
ただし形状や回転性能などにより取り扱いが変わる場合があります。
スロープの許容重量は200kgの案内例があります。
数値を基準に、現物の寸法をメモして共有するとスムーズです。
JPN TAXIの公式資料では、車いすの目安として長さ1200mm以内・幅700mm以内・高さ1300mm以内、スロープは200kg/300kgの記載があります。
目安となる長さや幅や高さが公開されています。
折りたたみ時のサイズ感も参考になります。
購入時の仕様表や取扱説明書を手元に置くと確認が早いです。
自分のベビーカーの横幅と奥行きと高さをセンチ単位でメモに残します。
ハンドルの角度やフットレストの位置で数値が変わることもあります。
双子用や海外ブランドなどは寸法が大きめの傾向があるため、現物での計測が役に立ちます。
配車前にアプリの備考へサイズを一行で書くとやり取りがスムーズです。
採寸用のメジャーをおむつポーチに入れておくと次回もすぐ測れます。
なお、国交省の「標準仕様UDタクシー」では車いすスペースの標準寸法を長さ1300×幅750×高さ1350mmと示しています。
折りたたまない場合、どこにどう固定されるのか
固定は車いす前提の設計です。
ベビーカーは動きやすい形状が多く、位置決めに工夫が必要です。
荷物や小物はまとめて動きにくい場所に置きます。
前向きと後ろ向きで収まり方が変わるため、向きを試してみます。
車輪のロックをかけ、取外せる小物は先にバッグへ入れます。
ハンドルの高さを一段下げると当たりにくくなる場合があります。
運転手さんと声を掛け合い、置き場所と手順を短く共有します。
固定のベルトやフックが使えない時は、人が近くで見守る体制にします。
“大きめベビーカー”は断られることも?(現場判断の実情)
車内スペースに収まらない場合は対応が難しいことがあります。
その際は無理をせず別車種や別便を検討します。
別の配車アプリで再検索する方法もあります。
フレームとシートを分けて載せると収まりやすいことがあります。
JPN TAXIやワゴンタイプを第一候補にし、次点の車種も用意します。
時間帯をずらすと手配の通りが良くなることがあります。
畳みやすい簡易タイプをサブとして用意しておく方法もあります。
当日の状況に合わせて、プランAとプランBを切り替えられる準備が心強いです。
ベビーカーとチャイルドシートは併用すべき?

チャイルドシートの取り扱い(タクシーでの適用除外の考え方)
幼児用装置の着用義務はタクシーで免除となる場合があります。
ただし家庭での移動方針との整合も踏まえて判断します。
携行タイプを選ぶ家庭もあります。
免除の扱いは国の定めに基づきます。
地域や事業者で運用に差が出ることがあります。
家族の希望と当日の状況を合わせて選びます。
携行タイプは重量や収納しやすさや装着時間も比較します。
予約前に使用可否をアプリの備考で伝えると準備が進みやすいです。
取扱説明書を写真で保存しておくと当日の確認が短時間で済みます。
根拠は道路交通法施行令 第26条の3の2 第3項第6号(タクシーは装置着用義務が免除となる場合あり)。
運用は地域や事業者で異なるため、予約時に方針を共有します。
最終的な取り扱いは、各自治体や事業者の最新案内をご確認ください。
抱っこ紐+シートベルトで移動する場合の注意点
抱っこでの移動は避けた方がよいと示す検証結果が紹介されています。
大人のベルトに子が絡む状態はずれやすいとされます。
可能なら座席に座らせる方法を検討します。
肩ベルトや腰ベルトの通し方に無理が出やすいことがあります。
急な加減速で体勢が乱れやすいとされる指摘もあります。
子が座れる場合は座席での着座を優先します。
眠っている時は起こさず、到着前にゆっくり体勢を整えます。
乗車前に必要な物を手元に集めて、体勢の変更回数を減らします。
JAFの検証では、抱っこ状態は保持が維持されにくい結果が紹介されています。状況により判断は変わるため、当日の様子に合わせて検討します。
座席利用のほうが体勢を保ちやすい場面があります。
子育てタクシーならチャイルドシートを事前予約可能
地域や会社により備え付けの有無が異なります。
予約時にサイズや年齢の情報を共有します。
当日の取り付け手順も事前に確認しておくと進行が早いです。
予約は前日までが通りやすい時間帯があります。
身長と体重と月齢の目安を一緒に伝えると合う機材が選ばれやすいです。
ISOFIXかシートベルト固定かを先に確認します。
取り付け位置の希望(後席右など)も共有します。
返却やキャンセルの連絡方法も合わせて確認します。
当日は受け渡しや装着の役割分担を決めておくと流れが整います。
乗車時の流れとスムーズに使うコツ

アプリでの指定時に備考欄に書くべき一文
「ベビーカーあり」「畳み可否」「手伝い希望」を簡潔に書きます。
目的地での降車位置の希望も添えます。
テンプレを端末のメモに保存しておくと毎回の入力が楽です。
台数が少ない時間帯は「JPN TAXI希望」「スライドドア希望」と一言添えます。
サイズは「横幅〇〇cm」「折りたたみ時〇〇cm」と数字で伝えます。
合流地点は「○○駅東口ロータリー」「○○モール南側車寄せ」など具体名を書きます。
雨の日は「屋根のある場所で合流希望」と記します。
- 例文A
- 「ベビーカーあり。畳めます。JPN TAXI希望。○○駅東口ロータリーで合流。」
- 例文B
- 「ベビーカーあり。畳めません。スロープ使用希望。○○病院正面車寄せで乗車。」
乗降場所の選び方(駐停車禁止エリアを避ける)
横断歩道や交差点の近くは避けて指定します。
見通しがよく停めやすい広めの地点を選びます。
歩道側に降りられる向きで停めてもらうと子連れでも落ち着いて動けます。
屋根のある車寄せやロータリーは集合がスムーズです。
段差が少なく平らな場所を選びます。
夜間は明るい位置を選ぶと手元の準備が進めやすいです。
人通りが多い駅前では一本裏の広い通りにピンを置くと合流しやすいです。
到着直前に目印をメッセージで伝えると見つけてもらいやすいです。
道路上での停車可否は地域の取り扱いに従います。
現地の標示や案内に合わせて指定してください。
スロープ準備に必要な時間と周囲配慮
展開と収納に少し時間がかかります。
人通りが多い場所では周囲への声かけが役立ちます。
準備中は子の手を取り、荷物はまとめておきます。
同乗者がいる時は役割を決めます。
一人は子を見守り、一人は荷物とドアの管理を行います。
雨の日はレインカバーとタオルを先に取り出します。
スロープを置く向きは段差に合わせて調整します。
到着後は荷物を先にまとめ、最後にベビーカーを整えます。
赤ちゃん連れのタクシー移動に役立つグッズ5選

静音おもちゃ・保冷シート・荷物まとめ袋など
音が控えめなおもちゃは車内でも使いやすいです。
季節によっては汗取りパッドやブランケットが役に立ちます。
買い物袋やポーチで小物をひとまとめにします。
音量を調整できるラトルや布絵本は周囲に配慮しやすいです。
クリップ付きトイで落下を防ぎやすく、拾い直しが少なくなります。
使い捨てエプロンやおしりふきはすぐ取れる位置に入れます。
おやつは一口サイズに小分けして、こぼれにくくします。
小さめのゴミ袋を数枚入れて、片付けを手早く終えます。
あると便利なタクシー内収納・整理グッズ
フックや小さなポケットで車内の一時置きが楽になります。
配車を待つ間に取り出す物だけを別袋にまとめます。
降車直前に必要な物は手前へ移動しておきます。
ヘッドレスト用フックにエコバッグを掛けると出し入れが整います。
シート背面のオーガナイザーはメモやペンの置き場になります。
ジッパーバッグで濡れ物と乾いた物を分けます。
重い物は足元ではなく動きにくい位置に置きます。
同乗者がいる日は受け渡し役を決めておくと流れがなめらかです。
移動中に子どもが過ごしやすくなる工夫
水分やおやつを準備します。
お気に入りのぬいぐるみがあると落ち着きやすいです。
景色の話題を振るなどコミュニケーションも取り入れやすい方法です。
到着までの目安時間を伝えると気持ちの準備がしやすいです。
短い読み聞かせや指遊びを交互に取り入れます。
窓の外の色や形を数えるミニゲームを楽しみます。
薄手の羽織りやレッグウォーマーで体温調整をこまめに行います。
眠そうな時は帽子やブランケットで光をやわらげます。
こまめに様子を見て、休みたい合図があればペースを落とします。
ベビーカーそのまま乗車が可能なエリアまとめ(主要都市)

東京:JPN TAXI普及状況と予約先
台数が比較的多く、時間帯によって呼びやすい傾向があります。
朝夕や雨の日は早めに手配すると待ち時間を抑えやすいです。
GOやS.RIDEのこだわり条件を活用します。
備考に「ベビーカーあり」「畳み可」「JPN TAXI希望」「平らな乗降場所希望」と一言添えます。
駅ロータリーや商業施設の車寄せなど、広い地点を地図ピンで示すと集合がスムーズです。
空港定額や事前確定運賃も確認します。
アプリ決済や電子レシートの設定も先に済ませておくと精算が短時間で済みます。
大阪・名古屋・福岡の対応アプリと事業者
地域によって主力アプリが異なります。
エリアごとの車種構成や台数の差もあるため、候補を二つ用意すると手配が通りやすいです。
アプリ内の地図で停めやすい場所を見つけて指定します。
地下街の出口近くや駅の高架下では、広い地点まで少し移動してから呼ぶと合流しやすいです。
事業者の特徴をメモにしておくと次回が楽です。
迎車料金や事前確定の可否、スライドドア比率なども一緒にメモします。
タクシー利用時によくある困りごとと対処のヒント

手配が難しかったケースと対応例
車内スペースに合わないと判断された事例があります。
サイズをメモして次回は車種指定を先に行います。
荷物を減らす工夫も役に立ちます。
畳み可否や横幅と高さをセンチでメモにまとめます。
備考欄には「ベビーカーあり」「畳み可」「JPN TAXI希望」と簡潔に書きます。
ピックアップ地点は広めの直線道路やロータリーを選びます。
車両番号と時刻を控え、次回の相談に活かします。
スロープ設置できなかった場合の代替手段
歩道の段差や傾斜で設置が難しいことがあります。
近くの平らな場所へ移動して再度試みます。
難しい時は畳んで乗る方法へ切り替えます。
設置方向を変えてもらうと届く場合があります。
五〜十メートル先のスペースへ下がると展開しやすくなります。
人が多い時間帯は一度畳んで乗り込み、到着地で広げ直します。
荷物は先に車内へ移し、動線を確保します。
忘れ物に気づいたときの連絡手順
アプリの乗車履歴から該当便を開きます。
GOのサポート&ガイドでは、利用履歴から該当の乗車を開き、タクシー会社へ連絡する手順が案内されています。
GOアプリの『メニュー>利用履歴・領収書発行』からご利用のタクシー会社を確認し、
営業所へ連絡できます。
会社の連絡先に時刻と行程を伝えます。
領収書の記載情報も手がかりになります。
品名や色や特徴を短く伝えます。
座った位置や置いた場所も添えると見つけやすくなります。
会社が不明な時はアプリのサポート窓口や地域の案内に相談します。
見つかった連絡先や受付番号をメモに残します。
おわりに:子どもとの移動をもっとラクにするために

今後増えるUDタクシーとその課題
導入拡大で選択肢は増えつつあります。
自治体の取り組みや車両の更新で、選べる場面がゆっくり広がっています。
一方で台数や場所の確保など運用面の課題も残ります。
乗降に向いたスペースの案内や、待ち合わせの工夫も引き続き求められます。
利用者の声が積み重なることで改善が進みます。
「畳まずに乗れる」が当たり前になる未来へ
配車アプリの指定機能が日々アップデートされています。
車いす対応やスライドドアの選択が見つけやすくなっています。
事業者側の対応可視化も進んでいます。
サイズの目安や備考のテンプレが増えると、呼び方に迷いにくくなります。
情報を共有し合うことで使いやすい環境が広がります。
状況に応じて「折りたたみ」と「そのまま」を使い分けよう
天候や混雑や荷物量で最適解は変わります。
近距離は動線を短くする考え方が役に立ちます。
遠距離は座席を確保してゆったり進む選択が合うことがあります。
無理のない方法をその都度選びます。
荷物が増える日はポーチで小物をまとめ、乗り降りを簡単にします。
家族のペースを大切にして移動を楽しみましょう。


